- #広告漫画コラム
SNSで炎上した企業の例と、炎上しない為の対策、炎上後の対処を解説!
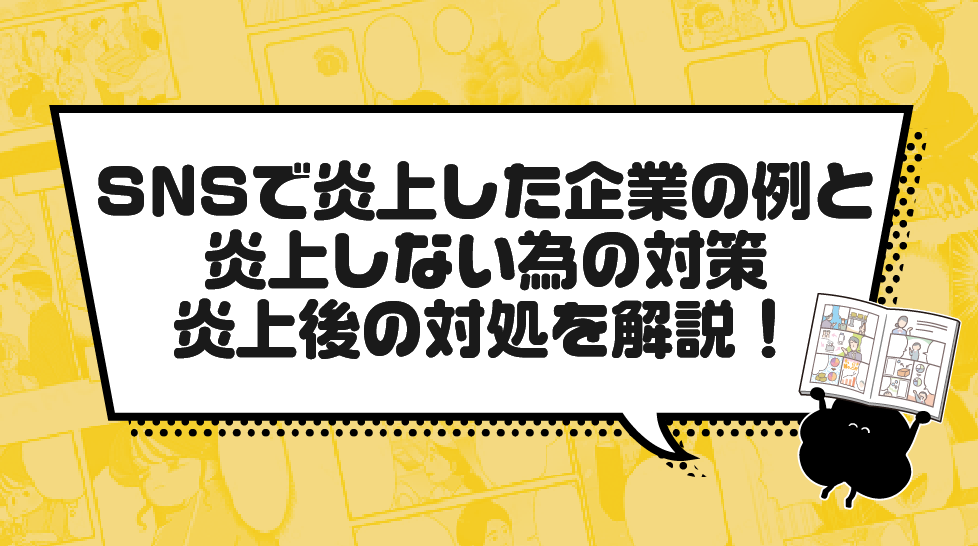
2025年もSNS炎上は企業広報の大きなリスクとなりました。AI広告・ジェンダー表現・政治家との距離感・転売記事など、炎上の火種は年々多様化しています。本稿では、5社の炎上事例を時系列で検証し、その構造や論点、各社の対応と世論の推移を整理。後半では、炎上を未然に防ぐための組織体制や投稿チェックフロー、教育手法としての“漫画教材”活用例まで解説します。
目次
2025年にSNSで炎上した企業の例
生成AI広告から政治家ポスト、備蓄米転売記事まで――今年もブランド毀損リスクは多様化し、想定外の角度から火が付きました。本コラムでは5社の最新炎上ケースを時系列で整理し、構造・論点・企業対応を検証。さらに、再発防止のためのガバナンス強化策と危機対応フローの作り方を解説します。
赤いきつね性的CM炎上問題
炎上までの経緯
- 2025年2月6日: 東洋水産が「赤いきつね」のアニメCMを公開。
- 2025年2月16日頃: 一部のSNSユーザーが女性の描写を「性的だ」と批判し始める。
- 2025年2月23日頃: 炎上がさらに拡大し、さまざまな意見が飛び交う。
- 2025年2月28日: 「非実在型ネット炎上」とも評され、別の視点からの議論が生まれる。
- 2025年3月22日: 日本経済新聞が炎上の経緯とSNS投稿の分析結果を報じる。
「赤いきつね」炎上のきっかけ
東洋水産の公式X(旧Twitter)で公開されたWeb限定アニメCM『ひとりのよると赤緑』が発端となった。主役は若い女性。恋愛ドラマを見て涙した後、自室でカップ麺「赤いきつね」をすすり、深夜の“ホッとするひととき”を過ごす様子を描いています。演出では「夜のリラックス感」を重視し、感涙や頬の赤み、髪を耳にかけるしぐさ、口元のアップなどが盛り込まれました。
SNS上の反応
「頬染め+すすり音+髪をかき上げるしぐさ」が性的フェティシズムを意識した描写ではないかと疑われ、「気持ち悪い」「男性目線で不公平だ」とのコメントが拡散。一方で、多くのユーザーやクリエイターは「グルメ漫画的な表現」「単に温かさを示す演出」と反論しました。人気料理研究家のリュウジ氏も「グルメ漫画で育ったので頬染めは普通の表現であり、性的とは思わなかった」と擁護しています。
「赤いきつね」の炎上構造と論点
1. 切り取り拡散
SNS上では演出の一部だけが切り出され、「セクシー映像」として拡散されました。マスメディア的な背景がそぎ落とされ、文脈を失った断片だけが残ったため、受け手の主観で自由に再解釈される状況が生まれました。
2. 非実在型炎上の側面
炎上は起きていたものの、投稿数は限定的で「実態のない大炎上」に見えた側面もあります。ただし、東京大学教授の調査では 2 月 16~17 日に 1 万件超の投稿が確認され、「小規模ではあるが実体のある炎上」と評価されています。
3. ジェンダー論争の影響
今回の批判はジェンダー・フェミニズム論争とも結びつき、SNS上ではいわゆる“ツイフェミ”の主張が盛り上がりました。これに対し、擁護派との間で激しい意見対立が発生しました。
東洋水産の対応
東洋水産は 生成 AI 使用疑惑を公式に否定し、関連情報の拡散抑制を呼びかけつつも CM は削除せずに公開を継続。2020年の「マルちゃん正麺」4コマ漫画炎上を教訓に、慎重な対応で沈静化を図りました。公式Xアカウントはフォロワー30万人突破を報告し、批判に屈せず発信を継続。その結果、支持の声が広がり、一部企業からの応援フォローも確認されています。
亀田製菓の移民に関する発言炎上問題
炎上までの経緯
- 2024年12月15日:AFP通信が、亀田製菓CEOによる「日本はさらなる移民受け入れを」という発言を報道 。
- 2024年12月16日以降〜2025年初頭:SNSで「反日・不買運動」の声が拡大、株価が下落。
炎上のきっかけ
2024年12月15日、AFP通信(仏語版はFrance 24)が〈Japan must admit more immigrants to thrive〉という見出しでジュネジャ・レカ・ラジュ CEO(インド生まれ)が語った内容を配信。「日本はさらに移民を受け入れるべきだ」という部分だけが切り取られ、日本語圏に拡散しました。
SNSでの反応
X(旧Twitter)で「#亀田不買」「#さよなら亀田製菓」が急上昇。右翼系インフルエンサーが“反日企業”と断定。「愛国心を踏みにじる反日発言」として不買運動や株価下落に発展。一方で「発言は誤訳」と擁護する声もあり、意見が分かれました。
炎上の構造と論点
1.情報の拡散と誤認
AFP通信の記事見出しや一部 SNS の煽り投稿が独り歩きし、事実関係の誤認が急速に拡大した。
2. ナショナリズムへの過敏な反応
「移民受け入れ」というテーマがナショナリズムを刺激し、感情的な批判が加速。
3. 言説の二極化
「誤訳」「ミスリードだ」とする擁護論も多く、擁護派と批判派が真っ向から対立する構図となった。
4. 亀田製菓の対応
公式声明は出されておらず、経営層は沈黙を継続。不買運動の長期化で株式時価総額は約25億円減少したと推計される。
マクドナルドの生成AI広告炎上問題
1. 炎上までの経緯
- 2024年8月17日:公式 X に、生成AIで作成した“美少女+マックフライポテト”PR動画を投稿。
- 投稿直後から「気持ち悪い」「不気味」「買う気がしない」といった批判が急速に拡散した。
2. 炎上のきっかけ
AI生成の“ほぼ実写”美少女を起用したポテトPR動画が、視聴者に違和感を与えたことが発端。
3. SNSでの主な反応
- 不気味の谷を指摘する声が多数。
- 「食欲が失せる」「ブランドイメージと合わない」といったコメントが相次いだ。
4. 炎上の構造と論点
- 不気味の谷現象:リアルに近いが完全ではないAIキャラが嫌悪感を喚起。
- クリエイティブとブランドのミスマッチ:従来の温かみあるCM路線とのギャップが大きかった。
- 技術過信への拒否感:AI では「人の心を動かせない」とする反発が拡大。
5. マクドナルドの対応
公式謝罪は出していないが、以降は AI を前面に出した広告を控える姿勢を示した。多くの報道が「次回以降はAI活用を見直すべき」と指摘している。
松屋の政治家来店ポスト炎上問題
1.炎上までの経緯
- 2025年2月21日:公式 X に河野太郎氏とジョージア大使の来店写真を投稿。
- 同日中に「政治的中立を欠く」「不買運動を呼びかける」などの声が SNS で拡散した。
2. 炎上のきっかけ
期間限定メニュー「シュクメルリ」を食べに来た河野氏とジョージア大使の写真を、店舗プロモーションとして公式 X に掲載したことが発端。
3. SNS での主な反応
- 「政治家を宣伝に使うのは中立性に反する」
- 「河野氏の過去発言を思い出して不快」
- これらが不買運動に発展する動きを見せた。
4. 炎上の構造と論点
- 企業アカウントの政治家紹介リスク:政治家を登場させるだけで“政治利用”と受け取られやすい。
- 過去発言への波及:河野氏の昆虫食推進など、別の論争が再燃し批判が拡大。
- 中立性への疑念:政治的トピックを商用目的で用いたことへの反感が強まった。
5. 松屋の対応
公式謝罪や投稿削除は行わず、該当ポストは現在も公開中。政治家登場を評価する声もある一方、「リスクを覚悟した投稿だったのでは」との分析も見られる。
メルカリの米転売記事炎上問題
1. 炎上までの経緯
- 2025年2月中旬〜3月:公式記事「メルカリでお米を販売しよう!」を公開。政府備蓄米の転売方法を解説し、SNSで批判が急拡大。
- 2025年5月26日:政府が備蓄米の市場放出を閣議決定。
- 2025年6月13日:メルカリが政府備蓄米の出品禁止を明言。
- 2025年6月23日:緊急措置令の改正により、フリマ全体で備蓄米の出品が全面禁止に。
2. 炎上のきっかけ
公式お役立ち記事で政府備蓄米の転売を推奨するかのような内容を公開したことが発端。
3. SNSでの主な反応
- 「備蓄米を商売にするのは悪質」
- 「緊急時の公共資源を転売対象にするな」
- 強い倫理的批判が集中した。
4. 炎上の構造と論点
- 公共資源の商用化への反発:政府備蓄米の個人販売は道義的に許されないとの声が多数。
- プラットフォーム責任:転売を助長する場としてのメルカリの姿勢が問われた。
- 法令とモラルのギャップ:出品禁止措置後も記事を残したままにした対応の遅れが批判対象となった。
5. メルカリの対応
3月以降、備蓄米の出品を禁止し、問題の記事も非公開に。しかし、初動の遅さがユーザーから厳しく指摘され、企業モラルと危機管理体制に疑問符が付く結果となった。
企業がSNSで炎上しないための対策方法
SNSは企業と顧客の距離を縮める強力なツールですが、使い方を誤れば一瞬で「炎上」し、ブランド価値や信用を大きく損なうおそれがあります。本稿では、炎上を未然に防ぐための予防策と、万一炎上した際の適切な対処法を紹介します。
1.投稿前のダブルチェック体制を整える
誤解を招く表現や差別的な内容、事実誤認は炎上の火種になります。社内で複数人が確認するチェックフローを設けましょう。
2.社員へのSNS教育を徹底する
社員の個人アカウントが原因で企業が炎上するケースもあります。SNS利用ガイドラインを策定し、定期的に研修を行いましょう。
3.社会的背景や時事問題に配慮する
時代や価値観は常に変化しています。特定の性別・人種・文化を揶揄する表現は避け、多様性への配慮を忘れないことが重要です。
4.自社アカウントの投稿目的を明確にする
売上向上かブランド認知かなど、目的を明確にし、それに沿った戦略的な運用を行うことで無用な炎上を避けられます。
5.炎上事例から学ぶ
他社の炎上事例を研究し、原因と対応の成功/失敗パターンを把握しておくことは非常に有効です。
企業が SNS で炎上してしまった場合の対処方法
状況を正確に把握する
まずは炎上の発端、拡散状況、批判の論点を冷静に整理しましょう。感情的な対応は逆効果です。
対応方針を早急に決定する
事実確認のうえ、謝罪が必要と判断した場合は、迅速かつ誠実に対応します。中途半端な釈明は火に油を注ぐ恐れがあります。
適切な謝罪文・説明文を発信する
公式声明には次の要素を盛り込むと信頼性が高まります。
- 問題発生の経緯
- 自社の認識と反省
- 今後の対応策
- 被害があった場合のフォロー
拡散防止・再炎上防止策を講じる
問題投稿の削除、関連コメントへの適切な対応、検索結果対策(SEO や SNS のモデレーション)などで二次被害の拡大を防ぎます。
再発防止に向けた内部対策を実施する
炎上後の信頼回復には、社内体制の見直しや再発防止策の公表が不可欠です。
漫画で学ぶ SNS 炎上ケーススタディ
複雑な炎上メカニズムや対処フローをマンガ教育教材 に落とし込むと、社員は物語を追いながら ‟自分ごと” として疑似体験できます。
漫画は ‟まず読んでみよう” という 興味喚起 を生み、ストーリー構成によって 理解促進 を後押しするため、座学より定着率が高いのが特長です。
またデータ納品のため全社員に回覧することで1人あたりの教育コストが下がり、長期的な研修資産として活用可能です。炎上事例のインパクトを可視化し、「何をすれば防げたか」を対話形式で示せるマンガは、ガバナンス強化と再発防止を同時に叶える実践的ツールと言えるでしょう。
まとめ
SNS は双方向のコミュニケーションが可能である一方、些細なミスが大きなリスクに直結します。企業は「炎上しない仕組みづくり」と「万が一の危機管理体制」をセットで整えておくことが不可欠です。日頃からの備えこそが、ブランドを守る最大の防衛策になります。
FAQ
企業がSNSで炎上しないための対策方法は?
企業がSNSで炎上しないためには、投稿前のダブルチェック体制を整え、社員へのSNS教育を徹底することが重要です。社会的背景や時事問題に配慮し、自社アカウントの目的を明確化することで、誤解や批判を防げます。また、他社の炎上事例を分析し、予防策と対応力を高める姿勢も不可欠です。
企業が SNS で炎上してしまった場合の対処方法は?
企業がSNSで炎上してしまった場合は、まず発端や拡散状況を冷静に整理し、対応方針を早急に決定することが重要です。謝罪が必要な場合は、経緯・反省・対応策を含めた誠実な声明を速やかに発信し、問題投稿の削除やモデレーションで二次被害を防ぎます。再発防止のためには、社内体制の見直しと具体的な改善策の公表が欠かせません。
SNS 炎上ケーススタディを漫画で学ぶメリットは?
SNS炎上ケースを漫画で学ぶ最大のメリットは、読者が“自分ごと”として疑似体験できる点にあります。漫画は興味喚起と理解促進に優れており、座学より記憶定着率が高くなります。物語構成により炎上の流れや失敗の本質を直感的に理解でき、「何をすれば防げたか」を対話形式で明確に示すことが可能です。また、データ納品によって社員全体での共有がしやすく、教育コストも抑えられ、継続的な研修資産として機能します。




