- #広告漫画コラム
効率的にリード獲得する方法を教えます!

マーケティング活動において「リード獲得」は、売上や成約率に直結する最重要施策のひとつです。しかし、多くの企業が時間やコストをかけても、質の高いリードを効率的に獲得できていない現状があります。この記事では、効率的にリードを獲得する方法について、実際の事例や具体的な準備手順とあわせて解説します。
マーケティング活動において「リード獲得」は、売上や成約率に直結する最重要施策のひとつです。
しかし、多くの企業が時間やコストをかけても、質の高いリードを効率的に獲得できていない現状があります。
この記事では、効率的にリードを獲得する方法を、実際の事例や具体的な準備手順とともに、徹底解説します。
リード獲得とは?

リード獲得とは、「リード=自社の商品やサービスに興味を持ち、将来的に購入・契約する可能性のある見込み顧客」を獲得することです。
顧客獲得のスキームではしばしば「リードジェネレーション」と呼ばれます。
例えば、以下のような行動をとるユーザーはリードと見なされます。
- サイトの問い合わせフォームから資料請求したユーザー
- 無料体験やトライアルに登録したユーザー
- セミナーやウェビナーに参加したユーザー
- メルマガやLINEに登録したユーザー
リード獲得の目的
新規顧客へのアプローチスキームは下記の通りです。
- リードジェネレーション(リード獲得)
- リードナーチャリング(見込み客を育てる)
- リードクオリフィケーション(見込み客を絞り込む)
- 商談・受注
リードナーチャリングについては、下記の記事で詳しく解説しています。
リードナーチャリングとは、見込み客(Lead=リード)を育成し(Nurturing=育てる)、購買意欲を高めて顧客へと導くマーケティング手法です。
具体的には、メール配信やセミナー、資料提供などを通じて、見込み客に継続的に有益な情報を提供し、関心を深めてもらう活動を指します。
これにより、見込み客との信頼関係を構築し、最終的な購買につなげることが可能となります。
リード獲得のための施策

リード獲得のための施策は、大きく分けて「オフライン」と「オンライン」の2つの領域に分類されます。それぞれの施策には特徴や強み、向いている業種や商材の性質があります。
まず、オフライン施策とは、対面や物理的な手段を通じてリードを獲得する手法です。たとえば、展示会への出展、セミナーの開催、ダイレクトメールの送付、テレアポ、飛び込み営業などがこれに該当します。これらの施策は、直接相手の反応を見ながら関係を築くことができるため、リードの「温度感」を把握しやすく、信頼関係を短期間で構築しやすいのが強みです。特にBtoB商材や高単価商材の場合、顔を合わせたコミュニケーションが成約に大きく影響するため、オフライン施策が有効に機能します。ただし、準備や実施に時間と費用がかかる傾向があり、リーチできる数にも限りがあるため、効率の面では注意が必要です。
一方のオンライン施策は、WebサイトやSNS、広告などのデジタルチャネルを活用してリードを獲得する方法です。代表的なものには、SEOによるオウンドメディア運営、リスティング広告、SNS広告、ウェビナー、ホワイトペーパーのダウンロードなどがあります。オンライン施策の最大の魅力は、リード獲得の「スピード」と「拡張性」にあります。ターゲットの行動履歴や興味関心を分析したうえで、パーソナライズされたアプローチが可能となるため、ニーズが顕在化している層にピンポイントでリーチすることができます。また、データによる成果分析や改善が容易なため、PDCAを高速に回すことができ、限られた予算内で高効率なリード獲得が可能になります。
このように、オフラインとオンラインはそれぞれ得意分野が異なるため、片方に偏るのではなく、自社の商材やターゲット、リソース状況に応じてバランスよく組み合わせていくことが、リード獲得施策を成功に導く鍵となります。リアルな接点で信頼を築きながら、デジタルで広範囲にカバーしていくことで、質・量ともに高いリード獲得を実現できるのです。
オフライン施策
| 手法 | 時間効率 | 費用効率 | 顧客の質 | 備考 |
| 展示会 | ★ | ★ | ★★★ | 導入検討層が多く、商談化率は高め。コスト・準備工数がネック。 |
| セミナー(Web含む) | ★★ | ★★ | ★★★ | 自主参加のためニーズ顕在層が多く、商談につながりやすい。 |
| DM(郵送/FAX) | ★★ | ★★ | ★★ | 開封率・反応率が低いため、質はやや低いがターゲット次第で有効。 |
| テレアポ | ★★ | ★★ | ★ | 決裁者に直接アプローチできるが、拒否率が高い。スクリプトが重要。 |
| 飛び込み営業 | ★ | ★ | ★ | 現代では非効率な手法。訪問許可のある業種・地域では限定的に有効。 |
| サイネージ広告 | ★★★ | ★ | ★★ | 認知度向上には有効だが、リードの質は期待しづらい。間接施策向け。 |
展示会(リアル/オンライン)

特徴
業界別のターゲットが集まるため、短期間で多くのリードを獲得可能。自社ブースへの来場者と直接対話でき、製品のデモや資料配布も可能。
メリット
- 高関心層と直接接触できる
- 導入検討段階の見込み客が多い
- 名刺交換や商談につながりやすい
デメリット
- 出展料・ブース装飾・人件費などのコストが高い
- 準備や当日の拘束時間が長い
セミナー(オフライン/ウェビナー)
特徴
専門性を活かして、ターゲットに知識提供や事例紹介を行いながら信頼を獲得できる。オンラインなら全国から集客可能。
メリット
- 自社の専門性をアピールできる
- リードの関心度が可視化しやすい(質疑応答・アンケート)
- 低コストで実施可能(特にオンライン)
デメリット
- 参加者数を集める難易度が高い
- 準備・登壇に工数がかかる
DM(ダイレクトメール/郵送・FAX)

特徴
法人ターゲットに対し、住所やFAX番号を使って直接アプローチできる伝統的な手法。開封率はやや低いが、接触は確実。
メリット
- オフライン層への訴求が可能
- Webに弱い層にも届く
- デザインやクリエイティブで差別化できる
デメリット
- リストの精度に大きく左右される
- 開封・反応率が低い場合がある
- 印刷・郵送コストがかかる
テレアポ(電話営業)
特徴
企業リストに対して直接電話をかけ、決裁者と話すことを目的とした即時性の高い手法。スクリプトの品質が鍵。
メリット
- すぐにリアクションが得られる
- 担当者の課題をヒアリングしやすい
- 商談設定につながりやすい
デメリット
- 拒否率・ストレスが高い
- 電話営業への抵抗感がある企業も多い
- リスト精査・オペレーター教育が必要
飛び込み営業
特徴
アポなしで訪問して商談を試みる手法。近隣地域・ターゲットエリアなどで活用されるが、現代では非効率とされることが多い。
メリット
- リアルな現場を把握できる
- 特定の業界では有効なことも(例:建設・製造)
デメリット
- 非効率かつ断られる可能性が非常に高い
- 移動時間や人件費のロスが大きい
- セキュリティ対策強化で訪問しづらい企業が増加
サイネージ広告(デジタルサイネージ)

特徴
駅やオフィスビル、エレベーター内などに設置されたディスプレイを通じて情報を発信する手法。視認性と訴求力が高い。
メリット
- 特定エリアでの高い認知獲得
- 記憶に残りやすくブランド強化に有効
- 動画やアニメーションで直感的に伝わる
デメリット
- 直接的なリード獲得にはつながりにくい
- 広告費が高く、ROIが測りづらい
- 効果測定が困難な場合も
オンライン施策
| 手法 | 時間効率 | 費用効率 | 顧客の質 | 備考 |
| オウンドメディア(SEO) | ★ | ★★★ | ★★ | 効果までに時間がかかるが、継続運用で圧倒的コスパ。 |
| リスティング広告 | ★★★ | ★★ | ★★★ | 顕在層が多く高精度。運用スキル必須。競争激化に注意。 |
| SNS広告 | ★★★ | ★★ | ★~★★ | 拡散力は高いが、購買意欲が弱い層も含む。 |
| ホワイトペーパーDL | ★★ | ★★ | ★★ | 精度の高いコンテンツ制作で質を高められる。 |
| オンラインセミナー(ウェビナー) | ★★ | ★★〜★★★ | ★★★ | 中〜高単価商材との相性◎。ナーチャリングにも有効。 |
| バナー広告(ディスプレイ) | ★★★ | ★ | ★ | 潜在層向け施策。直接的なリード獲得は難しい。 |
オウンドメディア(ブログ・SEOコンテンツ)

特徴
自社サイトに集客し、記事やホワイトペーパーで情報提供 → リード化
メリット
- 長期的に低コストで集客が可能
- 潜在〜顕在層まで幅広くアプローチできる
デメリット
- 効果が出るまで時間がかかる
- 継続的な運用とSEOスキルが必要
リスティング広告(Google広告など)
特徴
検索キーワードに連動して広告を表示。ニーズ顕在層を狙える。
メリット
- 即効性があり、明確なニーズに対応できる
- キーワード選定次第で高精度なターゲティングが可能
デメリット
- 広告費が高騰傾向(競合が多い業種は特に)
- LPやCVポイントの改善が必須
SNS広告(Instagram/Facebook/Xなど)

特徴
ターゲットの興味・属性に基づいて広告を配信できる。BtoC商材に強み。
メリット
- リーチが広く、ブランディングにも有効
- クリエイティブ次第で反応率UP
デメリット
- 購買意欲の高くない層も多く、質はやや不安定
- 運用ノウハウが必要
ホワイトペーパー・資料ダウンロード
特徴
業界ノウハウや導入事例などをPDF化し、ダウンロードと引き換えにリード情報を獲得。
メリット
- 課題解決意識が高いユーザーを獲得しやすい
- 資料の再利用性が高い(セミナーや展示会と連携可)
デメリット
- 質の低いダウンロード(情報収集目的)も多く混ざる
- コンテンツ制作に工数がかかる
オンラインセミナー
特徴
自社のサービスや事例をテーマにしたライブ配信。質疑応答でリードの温度感も確認可能。
メリット
- ハウスリストや広告から効率的に集客可能
- 参加者のニーズ顕在度が高く、商談化しやすい
デメリット
- 集客と登壇準備に一定のリソースが必要
- 定期開催で効果が持続
バナー広告(ディスプレイ広告)

特徴
Webサイト上に画像・動画で広告を出す認知拡大系の施策。GDNやYahoo!、業界媒体などで利用。
メリット
- 潜在層へのリーチに強い
- 大規模な認知拡大に向いている
デメリット
- CTR(クリック率)は低い傾向
- CVにつながりにくいため工夫が必要
効率的にリードを獲得するまでの準備
効率的にリードを獲得するためには、闇雲に施策を打つのではなく、事前にしっかりとした準備を行うことが不可欠です。なぜなら、リード獲得は単なる「数の勝負」ではなく、「質」と「再現性」が求められるマーケティング活動だからです。準備が不十分な状態では、ターゲットが曖昧なまま施策が走り、結果的に成約につながらない低品質なリードを大量に集めてしまう恐れがあります。
まず、目標が明確でなければ、何をもって「成功」と判断するのかが分からず、KPIの設定や効果測定ができません。次に、ターゲットとなる顧客像(ペルソナ)を定義していなければ、そのニーズに刺さる施策やコンテンツを設計することも困難になります。また、ペルソナに合ったチャネルや手法を選定しなければ、せっかくの時間と費用が無駄になってしまう恐れもあります。
さらに、時間や費用のリソースには限りがあるため、あらかじめどの施策にどれだけの投資ができるのかを見積もっておく必要があります。これにより、実行可能な範囲で最大限の効果を得るための配分が可能になります。そして、その投資がどれほどのリード獲得につながるのか、時間効率や費用効率といった視点からも算出しておくことで、実行後の効果検証や改善に活かすことができます。
最後に、実際のアクションとなるコンテンツ制作についても、ただ情報を発信するだけでなく、ペルソナにとって価値があり、行動を促す設計にすることが重要です。すべての準備を体系的に行うことで、施策の一本一本が連動し、無駄のない、精度の高いリード獲得につながります。
準備は、単に「やることを整理する」作業ではなく、マーケティング活動全体の成功確率を高め、再現性のある成果を出すための「戦略立案プロセス」と言えるでしょう。
1. 目標の明確化(KPI/KGIの設定)
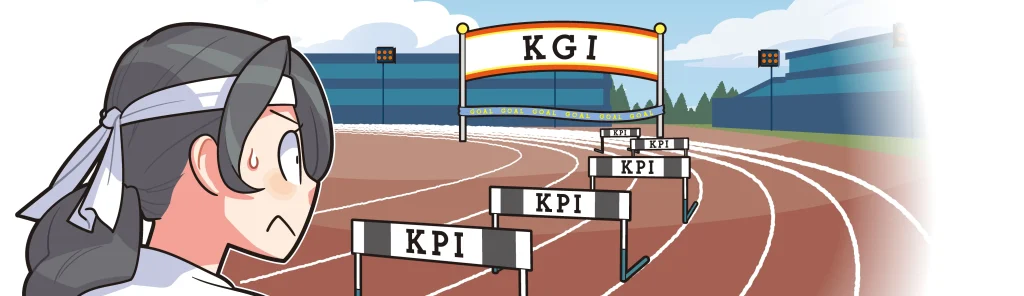
リード獲得の施策は、明確なゴールなしでは成果が測れません。まずは「何をもって成功とするか」を数値で定めましょう。
例:
- KGI(最終目標):半年で売上1,000万円を達成
- KPI(中間指標):月間ホットリードを50件獲得する
ポイント:
- 成約率や受注単価から逆算して「必要なリード数」を割り出す
- マーケ部門と営業部門で目標を共有する
2.ペルソナの設定(ターゲット像の明確化)
誰に対してリーチし、どのような課題を解決するのかを明確にします。 「年齢・職種・役職・悩み・メディア接触状況」まで詳細に設定しましょう。
ペルソナ例(BtoB):
- 45歳・男性・部長クラス
- 中堅メーカーの販促責任者
- DX推進ミッションを受けている
- Web広告よりも展示会やセミナーに信頼を寄せる
ポイント:
- 実際の顧客インタビューが有効
- 複数パターンのペルソナを用意してもOK
3. 施策を決める(チャネル戦略)
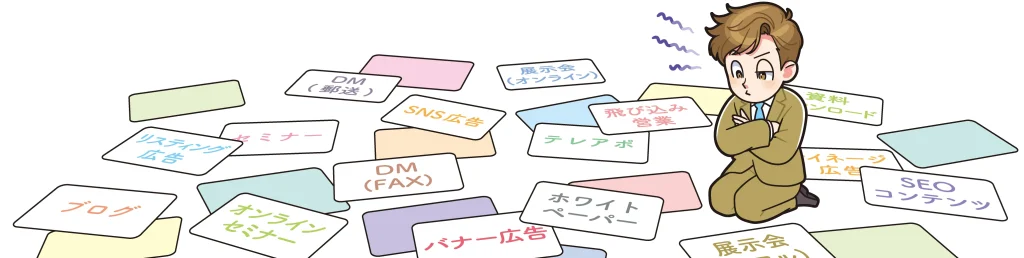
目標とペルソナが決まったら、最適なアプローチ手法を選定します。 オンライン/オフラインの両方を視野に、以下の要素を検討します。
検討項目:
- すぐに結果を出したい → 広告、テレアポ、ウェビナー
- 時間をかけてナーチャリング → SEO、ホワイトペーパー
- 質の高いリードを集めたい → 展示会、セミナー、資料請求
ポイント:
- 単独施策よりも、動線を設計した「連携型」のほうが効果的
- MAツールやCRMとの連携も視野に入れる
4. 時間・費用の予算を決める(リソース管理)
| 項目 | 内容例 |
| 時間の予算 | コンテンツ制作:週10h、営業稼働:月30hなど |
| 費用の予算 | 広告費:月30万円、展示会:年1回で80万円など |
| 人的リソース | 制作担当1名、営業2名、広告運用外注など |
ポイント:
- 社内リソースだけで対応できるか、外注が必要かを明確にする
- 突発タスクを見越して「余白」も予算に含める
5.獲得数/時間を算出する(時間効率の分析)
時間あたりにどのくらいリードが得られるのかを把握します。工数の多い施策に偏りすぎると、チームが疲弊するため注意が必要です。
計算例:
- ウェビナー準備(計20時間)→ リード40件 ⇒ 2件/h
- テレアポ(50時間)→ リード25件 ⇒ 0.5件/h
ポイント:
- 過去の実績やベンチマークをもとに試算する
- PDCAの材料にもなる
6.獲得数/費用を算出する(費用効率の分析)
こちらはCPA(Cost Per Acquisition)と呼ばれます。
費用あたりに何件のリードが取れているかを見ることで、投資対効果が分かります。
計算例:
- リスティング広告:月20万円 → リード40件 ⇒ 5,000円/件
- 展示会出展:80万円 → リード80件 ⇒ 10,000円/件
ポイント:
- ROI(成約率・単価)まで見ると精度が上がる
- 高CPAでも、質の高いリードなら「高効率」とも言える
7. コンテンツ制作(アセットの整備)

選んだ施策に応じた「フックとなるコンテンツ」を作成します。
情報提供型のホワイトペーパー、ランディングページ、広告バナー、セミナー資料などが該当します。
作成すべき代表的なコンテンツ:
- LP(ランディングページ)
- 資料ダウンロード用PDF(導入事例・課題解決事例)
- セミナー資料/動画
- ブログ記事/SEOコンテンツ
- SNS広告用の画像・動画
ポイント:
- ペルソナにとって「欲しくなる情報」を用意することがカギ
- 1つの素材を複数チャネルで活用できるように設計すると効率的
まとめ
リード獲得は、売上や成約率に直結する最重要施策です。効率的なリード獲得には、「オフライン施策(展示会・セミナー・DMなど)」と「オンライン施策(SEO・広告・ウェビナーなど)」をバランスよく活用することが鍵となります。
闇雲に施策を打つのではなく、目標(KPI/KGI)の設定、ターゲット(ペルソナ)の明確化、最適チャネルの選定、時間・費用効率の試算、コンテンツ制作まで、事前準備を徹底しましょう。
リード獲得は「数」だけでなく「質」と「再現性」を意識し、戦略的に進めることが重要です。
FAQ
リード獲得の方法とは
リード獲得施策は、オフラインとオンラインを組み合わせることが成功の鍵です。オフラインでは展示会出展やセミナー開催、DM・テレアポなどで直接対話し、リードの温度感を掴んで信頼を構築します。特にBtoBや高単価商材では効果的ですが、手間とコストがかかる点に留意が必要です。オンラインではSEO対策によるオウンドメディア、リスティングやSNS広告、ウェビナー、ホワイトペーパーDLなどを活用し、スピーディかつ拡張性の高いリーチを実現します。行動データを元にパーソナライズ配信し、PDCAを高速に回せるのも強みです。両者を目的・ターゲット・予算に合わせて最適配分することで、量と質を両立したリード獲得が可能になります。
オフラインのリード獲得の方法は?
オフラインでのリード獲得手法には、まず展示会やセミナー出展で直接見込み客と対話し信頼を築く方法があります。ダイレクトメール(郵送・FAX)はターゲットに確実に情報を届け、反応率を高めます。テレアポは電話で即時にアプローチできる一方、スクリプトの質が成果を左右します。飛び込み営業は特定業種で有効ですが非効率になりやすく、サイネージ広告は特定エリアでの認知向上に適しています。
オンラインのリード獲得の方法は?
オンラインでのリード獲得手法は、自社サイトに記事やホワイトペーパーを掲載しSEOで集客するオウンドメディア運用、検索連動型リスティング広告で顕在層を即時獲得、SNS広告で属性ターゲティング、ホワイトペーパーDLで課題意識高い層を囲い込み、オンラインセミナーで温度感の高いリードを商談化、バナー広告で潜在層の認知拡大を図ります。




